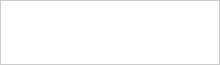こんにちは相厚エステートの添田です。
当社では様々な不動産の売却相談をいただいておりますが、今回のご依頼は「分家住宅」と「農家住宅」でした。

< このページの目次 >
分家住宅とは
分家住宅とは、市街化調整区域内の農地に建てた家のことを言いますが、だれでも建てれるわけではありません。下記条件を満たし、都市計画法34条の規定により開発審査会の許可を受けることができて初めて建築ができます。
- 建築の申請が出来る者は農家の家族で、分家した後も農業を営むことを認められた者であること
- 分家する者につき、一住宅一回限り
- 分家住宅の建築予定地は原則として本家と同一の集落内にること
- 建築予定地は原則として申請者がその土地を1年以上保有していること
- 予定地に住宅を建築しなければならない理由があること
建築する時も大変な手続きを必要としますが、売却するのも一般の住宅と比べ手続きが複雑なため不動産業者によっては「売却できません」と回答するところも少なくありません。
通常の不動産売買と比べ手間がかかるのでやりたくない、やり方がわからないというのが正しい説明でしょうか。
分家住宅を売却するには
一般の住宅は不動産に対して許可を取るので、その不動産に住む人を選びませんが、分家住宅の場合は住む人に対して許可をするので、許可を受けた個人しか住居することができません。
そのため不動産を売却をしても、購入者はその住宅に居住すると都市計画法の違反となり、退去命令や取り壊し命令が出ます。
建物を解体し、更地にすれば売却できますが不動産の価値が減ってしまうのが問題ですよね。
分家住宅から一般住宅への用途変更が必要です
やむを得ない理由で売却が必要となった場合は、一般住宅に用途変更する必要があります。
但し、下記の条件に該当し開発審査課の許可を貰う必要がありますのでご確認ください。
- 建築後20年以上経過していること(内容によって10年)
- 用途変更を行う者が10年以上居住していること(内容によって5年)
- 農業従事者としての資格を喪失したもの
- 生計維持者が亡くなった場合
- 破産宣告をした場合
- 住宅ローンの返済が出来なくなった場合
- 転勤、転地療養、離婚等家庭的な理由がある場合
- その他の明確な理由がある場合
厚木市では令和4年8月1日より用途変更の審査基準が緩和されました
一般住宅への用途変更が出来る条件
- 農家住宅または分家住宅の申請者が住んでいる
- 建築から20年以上経過し、10年以上居住した実績があること
- やむを得ない理由で施設などに転居している方
- 申請者の相続人
- 分家住宅以外で市街化区域の不動産を所有していないこと
8月1日以降、分家住宅に関する相談件数が増加し、一般住宅へ用途変更の許可申請手続きを行っておりますが、上記条件に該当している方は無事に許可が下りています。
大まかなスケジュール
- 事前審査書類提出から回答まで2~3週間
- 本審査の書類作成に1~2か月(現況図や測量図)
- 書類提出から許可まで1~2か月(農業委員会審査会の開催月によって異なります)
厚木市以外でも対応可能な市町村があるようなので、分家住宅の売却をご希望の方はお気軽にご相談ください。
農家住宅とは
上記で説明していたのは農家の家族が建てる分家住宅でしたが、今回は農家の本家が建てる農家住宅のことで下記の条件を満たした個人又は法人が建てることが出来ます。
- 10アール以上の農地を所有または所有以外の権限で耕作を行っている世帯(以下農家と言います)で一人以上の者が年間60日以上農業に農業に従事していること
- 10アール以上の農地を所有または所有以外の権原で耕作を行っている農業生産法人の常時従事者である社員又は法人で、その法人のぎょぎょ有無に必要な農作業に従事する者
- 年間における農業生産物の総販売額が15万円以上である事
- 農家住宅は一農家につき一住宅のみとする
売却相談をいただいた物件は下記の通り
- 個人の農家である
- 建築基準法の道路には接道していない
- 建物が建っている敷地の登記地目は宅地だが、隣接する四方の土地は全て田
- 建物は平成20年に新築しているが未登記
市街化調整区域内の田は農地なので農業従事者にしか売却が出来ません。しかも農家住宅は一農家一住宅のため農業従事者に売却をしても建物の使用は都市計画法違反となり認められておりません。よって売却方法は売主または買主の負担で建物を解体し、農地として売却するしかありません。
平成29年度田畑売買価格等に関する調査結果をみると、関東地域の田んぼの平均価格は10アール161.9万円(1619円/㎡)、畑の平均価格は10アール170.4万円(1704円/㎡)となっておりますが、農地は売りたい農家は多くても買いたい農家が少ないので農地の売買は簡単には行きません。
が、一定の基準を満たしていれば農地でも売却する方法はあります。
農地の売却
農地とは市街化調整区域内の田や畑のことを言います。上記の農家住宅と同様に田や畑は農地法という法律で農業従事者同士でしか売買は出来ないようになっていますが例外があります。
田や畑でも雑種地や山林に地目変更が出来れば売却できます
全ての田や畑の地目変更をする事は出来ませんが、農業委員会や開発審査課の許可を受けることが出来れば、地目変更や用途変更をする事が可能です。
地目変更が認められる例として、広い道路に面している農地であれば、休耕地を資材置場にしたりコンビニエンスストアや大型スーパー、物流倉庫になっているのを見たことがあると思います。
また、都市計画道路等の公共事業用地に絡んでこれば代替地として宅地に変更できる事もあります。
農地の売却については別の記事で詳細を説明させていただいております。
まとめ
当社がある神奈川県厚木市は全体の50%が市街化調整区域に指定されている為、市街化調整区域の不動産売買は熟知しております。過去に売却の相談をして「売れません」と回答されてしまい諦めていたお客様は一度、相厚エステートまでご相談ください。